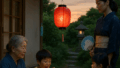今日は7月23日、「米騒動の日」。
1918年のこの日、富山県魚津町の漁師の妻たちが米の高騰に対して声を上げ、集団で抗議を行ったことが、全国的な民衆運動のきっかけとなりました。
この出来事は、日本初の本格的な民衆による生活要求運動として歴史に刻まれており、その波は全国へ広がり、社会の変化を促す大きなうねりとなりました。
「米」をめぐる生活の重さ
現代においては、コンビニやスーパーに行けば、さまざまな食品が当たり前のように手に入る時代ですが、ほんの100年前の日本では、「米」の価格の高騰が家庭の生活を直撃する死活問題でした。
あの日、声を上げたのは、漁村で暮らすごく普通の主婦たちでした。
決して特別な活動家ではなく、日々の家事や育児、そして生活を守るために踏み出した一歩だったのです。
彼女たちは、声を上げることが「秩序を乱すこと」だと非難されるかもしれないという不安の中、それでも黙ってはいられなかった。
そこには、「家族を飢えさせるわけにはいかない」という、ひとりの母親としての覚悟があったのでしょう。
小さな声の持つ力
その抗議は一時的なものでは終わらず、徐々に各地へ広がり、大規模な暴動へと発展し、最終的には当時の内閣が総辞職するという、政治を動かす事態にまで至りました。
まさに、「民の声」が国の形を動かした瞬間だったのです。
私は、このような出来事があったことを、学生時代の授業で初めて知りました。
教科書の中では数行に収められていた記述でしたが、「なぜ主婦たちが先陣を切ったのか」「なぜその声が無視できなかったのか」と考えるうちに、そこには“暮らしの中の切実な痛み”があったのだと気づかされました。
いま私たちができること
現代の日本において、生活そのものが危機にさらされるようなことは少なくなりましたが、それでも物価の上昇や格差、孤立といった問題は、形を変えて私たちの身の回りに存在しています。
SNSやネット社会の中で、「声を上げる」ことが以前よりは簡単になったように思えますが、本当の意味で他者と向き合い、連帯し、社会に届く声を発することの難しさは、今も変わらないのかもしれません。
だからこそ私は、日々の生活の中で、どんな小さな声にも耳を傾ける姿勢を大切にしたいと思っています。
「これは些細なことだから」「こんなこと言っても仕方ない」と自分に言い聞かせて飲み込んでしまう思いの中にこそ、次の時代を動かす“芽”があるのではないでしょうか。
暮らしと心の輪郭を支えるために
日々、私は「処分」という仕事を通じて、多くの方々と対話しています。
とくにラブドールのご依頼では、誰にも話せなかった想いや、過去との向き合い方に触れる機会も多く、その一つひとつに重みを感じます。
物を手放すという行為は、決して物質的な行動だけではありません。
その裏には、「自分の思いを整理したい」「次へ進みたい」という心の声が、確かに響いているのです。
ラブドールという存在は、使われなくなったからといって無機質なゴミになるわけではありません。
それはかつての時間や感情を映した“存在の記録”であり、だからこそ処分には大きな決意が必要です。
私は、そのような気持ちに寄り添いながら、お客様の声に耳を傾け、丁寧な対応を心がけております。
処分用段ボールの特注、納期の調整、梱包時の配慮など、どの工程においても「安心して託せること」を第一に考えております。
もし、「誰にも相談できない」「こんなことを依頼しても大丈夫だろうか」と迷われている方がいらっしゃいましたら、どうかご安心ください。
その声が届くように、私は今日も静かに仕事を続けております。
そして、心の整理をするその一歩を、どうか大切にしていただければと願っております。
本日も、過去に敬意を払いながら、いま目の前の声に向き合う一日でありたいと思います。