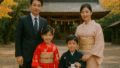今日はベルリンの壁崩壊の日だと、朝のニュースであらためて耳にしました。1989年11月9日。あの日、遠いヨーロッパの街で起きた出来事は、当時の日本の小学生だった私にとっては、どこか現実感の薄い「世界のニュース」でしたが、それでも強く印象に残っています。
あのころの我が家では、夕食の時間になると自然とテレビがニュースに変わりました。大阪の小さなダイニングテーブルに家族がそろい、ちゃぶ台代わりの机の上には、焼き魚や味噌汁、湯気の立つご飯茶碗。その向こう側のテレビ画面には、見たことのない外国の街並みと、人々の歓声、そして分厚いコンクリートの壁が映し出されていました。
ハンマーや素手で壁を崩している人たちの姿、肩車された子ども、抱き合って泣いている男女。まだ小学生だった私は、「どうして壁を壊しているのか」「この人たちは何をそんなに喜んでいるのか」がよく分からず、箸を持ったままじっと画面を見つめていたことを覚えています。
「これはベルリンの壁っていうんやで。長いこと町が二つに分かれてたのが、やっと一つに戻ろうとしてるところや」
父はそんなふうに、簡単な言葉で説明してくれました。けれども、「国が分かれる」「町が分かれる」という感覚は、当時の私にはあまりに抽象的で、ピンと来ませんでした。ただ、「壁があると家族でも会えない人がいるらしい」という一言だけが、子ども心にとても怖く感じられたのを覚えています。
翌日、学校へ行くと、社会科が得意な先生が黒板に簡単な地図を描いて、「昨日、歴史が動きました」と少し興奮気味に話していたことも記憶に残っています。日本の教室の中で、遠いヨーロッパの話を聞いている自分との間に、不思議な距離感がありました。「歴史が動く」という言葉は分かったような分からないような感じで、でも、先生が本気でそう言っているのは伝わりました。
今振り返ると、あの日の映像は、世界が「目に見える境界」をひとつ乗り越えた瞬間だったのだと思います。当時は冷戦という言葉の意味もろくに知りませんでしたが、あの夜、壁の上で歌ったり踊ったりしていた人たちは、それぞれに長い不安と不自由を抱えて生きてきたのでしょう。その積み重ねがようやくほどけて、「自由」という言葉が具体的な手触りを持ちはじめたのが、あのタイミングだったのかもしれません。
大人になってから、写真集やドキュメンタリーを通してベルリンの壁の歴史を知るようになり、改めてあのニュース映像を思い出すと、あのときの自分の「よく分からないけれど胸がざわざわする感じ」に少し説明がついたような気がします。分断や境界というのは、目に見える線だけの問題ではなく、人の心の中に生まれる「こちら側」と「あちら側」の想像力の欠如でもあるのだと感じます。
大阪のような大きな街で暮らしていると、人種や国籍、価値観の違う人が同じ電車に乗り、同じ通りを歩きます。時には摩擦もありますが、本来はその「ごちゃ混ぜ」が、この街の豊かさでもあります。ベルリンの壁の崩壊を思い出すたびに、「見えない壁」を自分の中につくらないようにしたい、とあらためて思います。分からないものを、すぐに怖がったり排除したりせず、一度立ち止まって「なぜそうなっているのか」と考える余裕を持ちたいものだと感じます。
子どものころ、ニュースの画面の中で砕け散っていたのはコンクリートでしたが、あの日を境に崩れ始めたのは、もっと大きな意味での「決めつけ」や「諦め」だったのかもしれません。私自身の生活の中にも、小さな壁はたくさんあります。「どうせ分かってもらえないだろう」「これはこういうものだ」と自分で決めてしまっていることがどれだけ多いか、ときどき振り返る必要があります。
ベルリンの壁崩壊の日にあらためて思うのは、「世界の歴史」は教科書の中だけにあるのではなく、あの日テレビの前でスープを飲んでいた小学生の私のように、ひとりひとりの暮らしの記憶にも静かに入り込んでくるものだということです。そして、その記憶をどう受け止め、どう次の世代へとつないでいくかは、今を生きる私たちに託されています。
今日の大阪は、あの日と同じように、夕方になれば電車が混み、スーパーにはいつものように人が並び、ニュースでは別の出来事が淡々と流れていきます。それでも、11月9日という日付がカレンダーにある限り、世界のどこかで「壁」が崩れ、またどこかで新しい「橋」が架けられているのだと想像したりしました。
ベルリンの壁崩壊のことを思いながら振り返ると、「見える壁」だけでなく、「心の中の見えない壁」についても考えさせられます。実は、ラブドールの処分についてご相談くださるお客様の中にも、ご自身の中に小さな壁をつくってしまい、なかなか一歩を踏み出せずにおられる方が少なくありません。
「恥ずかしくて誰にも相談できない」「こんなこと頼んでも大丈夫だろうか」「手放したいけれど、決心がついたりつかなかったりする」――そういったお声を本当によく伺います。
ラブドールの処分は、単に大きな荷物を片付ける作業ではなく、過去の自分との向き合い方や、これからの暮らし方を静かに選び直す行為でもあると感じています。ですから、迷いがあって当たり前ですし、「すぐに決めないといけない」というものではありません。お問い合わせも、最初は費用や流れの確認だけで構いませんし、そこでいったん立ち止まっていただいても大丈夫です。「やっぱりお願いしたい」と思われたタイミングで、改めてご連絡いただければ結構です。
実務的な面では、当方では秘密厳守を徹底し、外から中身が分からない形でお送りいただけるよう、ラブドールのサイズに合わせた特注段ボールをご用意しております(通常の納期はおよそ1週間ほどです)。受け取り拠点は大阪市旭区に加えて守口市にもございますが、どちらへお送りいただくかは、決済完了後にお届けするご案内メールに記載の住所が正式な送り先となります。お手元で迷われないよう、その時点で最適な宛先をご案内いたしますので、ご安心ください。
長く共に過ごしたものを手放すことは、簡単な決断ではありません。それでも、「今の自分の暮らしに合う形に、少しずつ整えていきたい」と感じたとき、そのお手伝いができればと思っております。ベルリンの壁が少しずつ崩されていったように、心の中の小さな壁も、一度にすべてではなく、少しずつ取り払っていけば良いのだと思います。
ラブドールの処分について、もし気がかりなことがございましたら、どうぞ小さなことからでもお尋ねください。お一人おひとりのペースに合わせて、静かに寄り添いながら対応させていただきます。